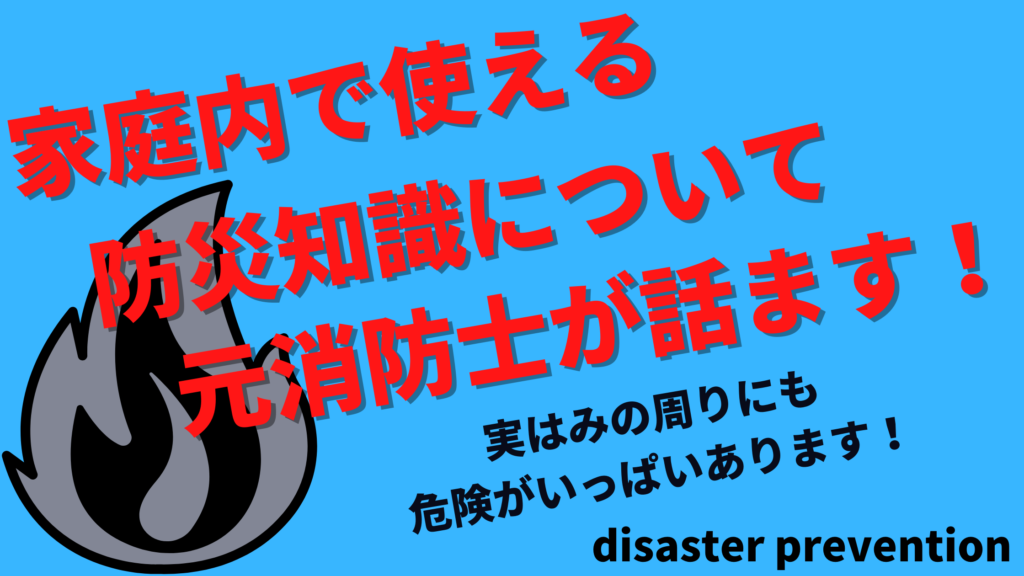
本日は「家庭内で使える防災知識について元消防士が話します!実は身の回りにも危険がいっぱいあります!」ということで話ます!
ということで話しをしていきます。
私は、2021年3月までは東京消防庁の消防士として仕事をしていましたが、新しいことに挑戦したいという気持ちから消防士という安定した職場を離れました。
そんな現在は、コーチングとブロガーをしています。
コーチングとは、「クライアントが主体的に深く考え行動できるように、対話をして支援すること」です。
コーチングを受けることで、あなたの目標達成能力や、幅広い視点で物事を捉えたりする能力が向上します。
以下に「ON/COA」のホームページおよび、notoに詳しく概要を書いていますので、ぜひご参考にしていただけると嬉しいです。

ON/COA:http://on-coa.com
noto:https://note.com/ryota_lifehack/n/n07e8eee6887b
消防士になるためのロードマップ:
https://note.com/ryota_lifehack/n/nce383cdb0a24
それでは本題!
みなさんは防災について考えたことはありますか?
実は考えたこともない方も多いのではないかと感じますか?
特に大きな災害(地震や台風など)では様々な対応していくことがありますが、実はそのほかにも家の中には様々な危険が潜んでいます。
という事で今回は
「知っておくべき防災知識(家編)」について話をしていきます。
元消防職員としてとして多いと感じるものを紹介していきます。
ぜひ最後までみてみてください!
それではいてみましょう!
知っておくべき防災知識(家編)
- コンセントのホコリに注意
- 屋根裏の掃除をしっかり・コードに注意
- 油に水を注がない
- タバコは必ず水につける
- ストーブに物を近づけない
- 住宅用火災警報器を付ける
コンセントのホコリに注意
みなさんは、半年に一度もしくは一年に一度は家の中にあるコンセントを見回っていますか?
特に、つけっぱなしになっているコンセンとは確実にみておくことをおすすめします。
というのも、コンセントの周りには基本的にホコリが溜まりやすくなる傾向にあります。
それは、コンセント部分のでっぱりが原因です。
コンセントの出っ張りをできるだけなくすためにL字に曲がる物もありますが、はっきり言って収納面だけは優秀ですが、むしろ隙間ができにくくなる事で、ホコリのたまり方はひどくなる場合もありますので、大丈夫だと思わないようにしてください。
そのホコリが原因で結構怖い家事が起きます。
以下の動画はコンセント周りに詰まったホコリからトラッキング現象によって起こる火災の実験映像になります。
これ、実はけっこう多い火災の現象の一つとも言えます。
特に、常時ついているコンセント部分には気をつけた方がよろしいですね。
例えば、冷蔵庫やエアコン、さらにはテレビのコンセントなど結構いろんな部分が常時刺さっているコンセントの位置になっていることが多いですよね?
少なくとも一年に一回以上、または半年に1回程度はコンセント周りのホコリやプラグに気をつけて点検をしていきましょう。
屋根裏の掃除をしっかり・コードに注意
これは戸建て住宅でよくある現象です。
しかし、マンションでもないとは言い切れないことになります。
実は、屋根裏のコンセント類、そして室内のコンセント類について注意しなければなりません。
まずは屋根裏部分からいってみましょう。
屋根裏のある戸建て住宅では、屋根裏部分に電気関係の配線をしていることもあります。
特に古い戸建て住宅なんかだと当たり前になっているかもしれません。
しかし、そこを掃除しておかないと、ネズミがでたり何か動物が住み着いてしまうこともあります。
そうすると、動物によって電気配線のコードを切られることから火災に発展してしまうことがあります。
以下の動画をご覧ください。
このように、電気配線のコードそのものが熱を持ちます。
そして、劣化さらには動物によって噛みちぎられたコードを使用することによって以下の動画のように、以上発熱を起こすことから火災につながっていることがあります。
電気機器を使うということはこのような責任が伴ってきますので、屋根裏を持つ戸建て住宅の方は確実に点検を行なっておきましょう。
さらに、これはマンションに住んでいる方やアパートに住んでいる方も例外ではありません。
みなさんの身の回りにはたくさんの電気機器が存在していますよね?
よく見かけるのはドライヤーのコードですね。
ジムのドライヤーのコードはぐちゃぐちゃになっているので私は毎回治すようにしています。
各ご家庭のドライヤーのコードはコンセントプラグを抜いてコードをきれいに束ねて収納していますか?
そのほか、パソコンのコードはぐちゃぐちゃになっていませんか?
割と身の危険はすぐ近くにあるということを自覚しておく必要がありますね!
油に水を注がない
天ぷら油など熱せられた油が燃えたとしても絶対に水を注がないでください!
以下の動画のように油に水を注ぐと、油と水は混ざり合うことがなことから、熱せられた油に水を入れると油の表面で水が走ることで延焼拡大になりかねません。
人は思いもよらないことが起きたとき、著しく判断能力が損なわれることから本当に水をかけてしまいうんですよね。
これは本当にやめてくださいね!
確実に消化器具を使って消化をしましょう。
消化器具のない方はこの機会に購入していただくか、家の近くにある消化器の位置を把握していち早く消化できるようにしておきましょう。
タバコは必ず水につける
タバコの火災は毎年行なっている火災の原因調査を集計したものでも上位に来ていることから気をつけている方も多いのではないかと感じますが、実際にタバコによる火災を見たことがある人は少ないのではないでしょうか?
ということで以下の動画をご覧ください。
これは寝タバコによる火災発生の動画です。
こうなってしまうから気をつけましょうという注意喚起が各自治体の消防署から出ているわけです。
タバコは消したし、俺は大丈夫。
そうではありません。
実は、タバコも火種が残り、不意にもそのひだねが布団や布などに飛び散ったとしましょう。
その火だねが12時間後や24時間後になってから再燃してしまうということがあります。
そのため、火災の消化活動が終わってからも、交代をしながら現場の再燃を防ぐために消防車を近くに止めているということがあります。
タバコを吸われている皆さんは本当に注意してください。
そして、灰皿内部にあるタバコを確実に水に浸しておくことで火災を防ぐことができるので、できる限り吸い殻は水につけておくことがベストです。
ストーブにものを近づけない
これは夕方のニュースで見た事があるかたも多いのではないでしょうか?
特に、寒い季節には重宝されている方も多いのではないかと感じます。
灯油の持ち運びもあることから、マンションよりも戸建て住宅での使用率が高いのかな?と感じます。
若い世代の方だと、エアコンの暖房機能で冬を乗り切っている方の方が多いのではないかと感じます。
しかし、若い世代の方が気をつけなければいけないのが、電気ストーブですよね。
作業机の下に入れてはいませんか?
そう、ストーブも形態は違くても使われている世代は幅広いので、自分は大丈夫と思わないでくださいね!
ストーブの近くには必ず一定距離を開けて物を置くようにしましょう。
皆さんもご存知のような火事につながります!
住宅用火災警報器をつける

皆さんは住宅用火災警報器を取り付けていますか?
これはつけておいて絶対に損のない物なので、必ずつけておくことをお勧めします。
長いので住警器と略します。
住警器は電池の寿命(約10年)によりなってしまうこともあるのですが、いち早く火災を突き止めるということに利点があります。
例えば、先ほど出したようなコード関係の火災だと仕事中や旅行中にあってもおかしくない火災の種類だと、どうなるでしょうか?
いち早、くその火災警報器に気がついた人が通報していれば火災は最小限に抑えることができます。
これは寝ている時も同じで、火災警報器が作動する事でいち早く火災に気が付き初期消化で終わらせる事ができる可能性があります。
火災の対応には速さが命となりますので、住警器をつけてより安心して暮らせる日常にしてください。
火事によって全て奪われる前に
皆さんは家事の現場を見たことがあるかわかりませんが、私は実際に消防士をしていたので、火事の現場には何度も行ったことがあります。
何もなく終われば本当によかったなと思っていました。
しかし、中には本当にひどい現場もたくさんあります。
ストーブ火災よって部屋のほとんどが焼かれ、家具や電子機器、さらには皆さんの大切にしているお金や思い出の品など全てがまる焦げになります。
何も戻っては来ません。
そんな悲しい思いをする前に対策できることはたくさんあります。
ぜひこの機会に家の中を見渡して危ない場所はなさそうか、火災に対応できるものは揃っているか今一度確認してみてください!
ちょっとの努力が皆さんの大切なものを守ることにつながるかもしれません!
最後に
最後までご覧いただきありがとうございました!
いかがでしたか?
ここまでちゃんと火災の動画を見たことがあるかたは少ないのではないでしょうか?
ニュースで見る家が燃えている映像はわかるけど、こんなふうにして燃え広がっているということがこの記事で伝わっていれば嬉しいです!
また、これをきっかけに何か対策をしていただけるともっとうれしいです!
また、元消防士として様々なブログを書いていますので、以下の記事ももし良ければ参考にしてみてください!
それではまた!
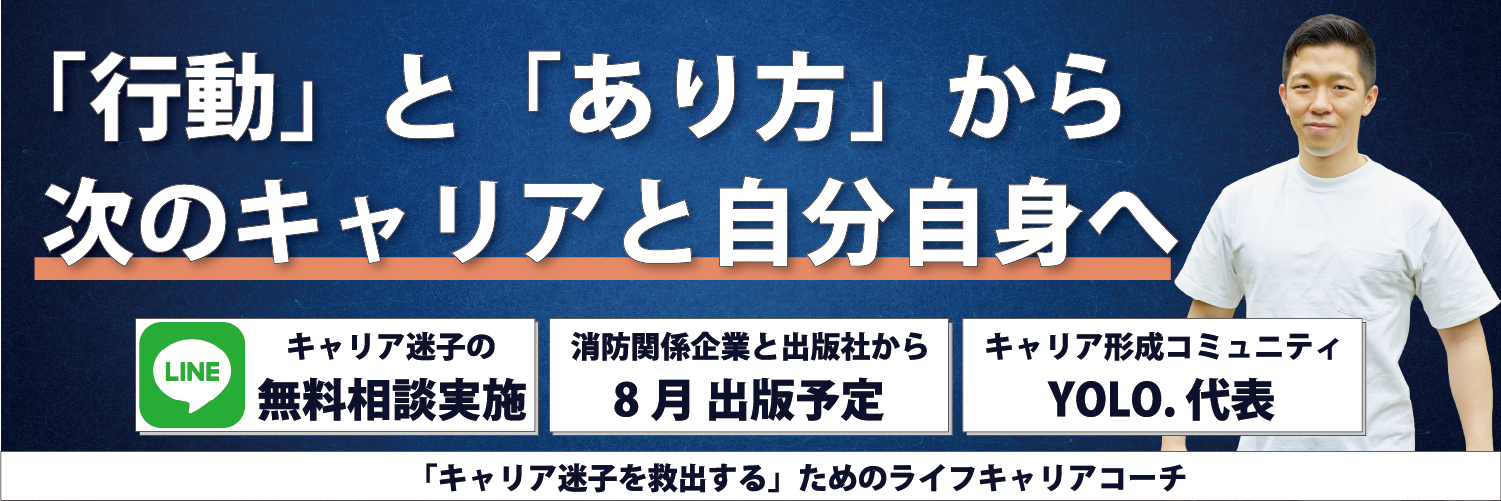
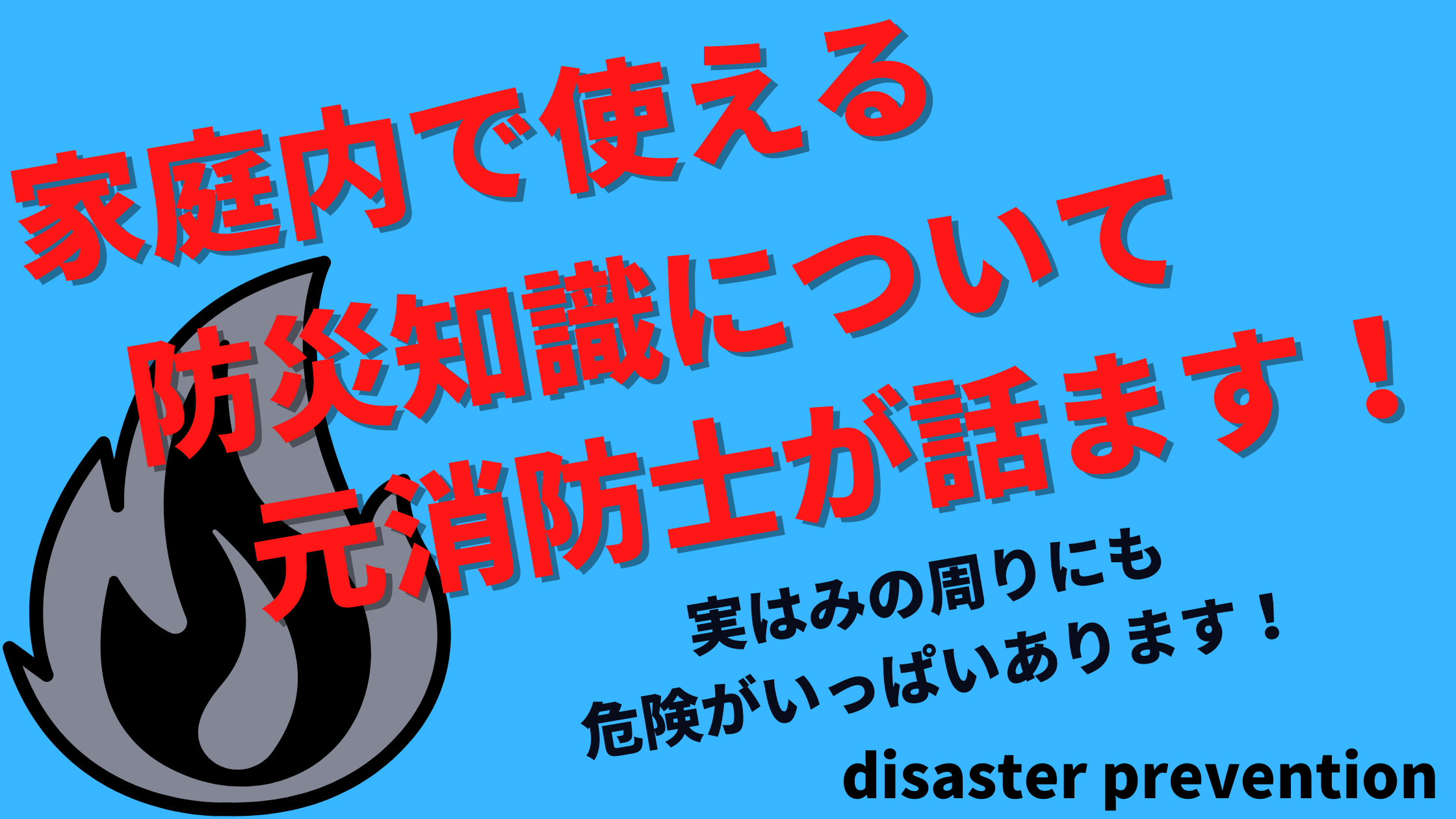


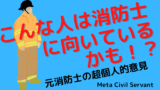
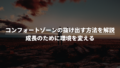


コメント